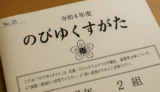「読み書きが苦手な子に、放課後の支援はあるの?」
「放課後等デイサービスって、実際どんなところ?」
発達に課題のある我が家の子どもたちの成長を見守る中で、放課後等デイサービスという存在に出会いました。今回の記事では、体験談や見学した施設の印象、利用するまでのハードル、そして実際に使わなかった理由なども含めて、リアルな視点からまとめてみました。

学習障害の息子2人の母
ぴーたん
25年間高校教員を勤め、現在は特別支援学校勤務。
これまで、多くの発達特性のあるお子さんたちと接してきました。
私自身、学習障害のある息子たちを育てながら、家庭と学校の両面からサポート。
このブログでは、保護者の「どうしたらいいの?」に寄り添い、実体験や役立つ情報をシェアしています。
さらに詳しいプロフィールはこちら。
放課後等デイサービスとは?制度と対象年齢
放課後等デイサービスとはどんな制度?
放課後等デイサービスは、障害のある子ども(主に6歳〜18歳)を対象にした、放課後や休日の療育・支援施設です。2012年の法改正で制度化され、現在では全国に多くの事業所が存在します。
対象となる子どもと必要な書類
知的障害や自閉症スペクトラムだけでなく、学習障害(LD)やADHDなどの発達障害の子どもも対象になります。手帳の有無は関係なく、「受給者証」があれば利用可能。取得には医師の診断や教育センターでの発達検査が役立ちます。
学習障害の子にとってのメリットと悩み
学習支援を目的に利用できる?
デイサービスには学習支援に力を入れている施設もあります。読み書きや計算など、LDの子どもが苦手としやすい分野に、作業療法士や言語聴覚士が個別で対応してくれることもあります。
学習支援を求めて見学したが…
私たちも、次男の読み書きの困難が気になり、小学3年生のときにいくつかの施設を見学しました。「書く」ことに苦手さがあり、1年生の漢字も定着せず、ひらがなカタカナの使い分けもあいまい。
デイサービスの個別支援に希望を抱いていましたが、実際には希望者が多く、枠が取れず通うには至りませんでした。
利用にはハードルもある
多くの施設が人気で、体験後に「空きが出たらご連絡します」と言われてそのまま…というケースも。実際、我が家も3年以上待っている間に、子どもは中学生になってしまいました。
実際に見学した放課後等デイの印象
支援の手厚さと専門性
見学した施設では、言語聴覚士による個別支援が受けられ、トレーニングの様子も保護者がマジックミラー越しに見ることができました。
作業療法士も常駐していて、学習だけでなく運動や生活支援にも対応。教育センターの担当者からも「ここは珍しくしっかりした施設」との声がありました。
学校との連携がある施設も
通っている学校への巡回支援を行う施設もあり、先生への指導提案やアセスメントを共有してくれる場合もあります。学習だけでなく、集団活動や社会性の育成にも力を入れている施設も多いようです。
利用料の負担は?
受給者証を取得すれば、基本的に1回1000円程度(1割負担)で利用可能。利用頻度や世帯収入によって月額上限が設定されています。
放課後等デイサービスの注意点
質のバラつきがある?
法律改正で一気に増えた放課後等デイサービス。中にはスタッフの専門性が低く、ただ預かるだけになってしまっているケースもあるとの話も。教育関係者やケースワーカーからは「必ず見学して、支援内容を確認してください」とのアドバイスもありました。
「支援級に通っていないと難しい」場合も
我が家の場合、支援級に在籍していなかったため、施設側から「他の利用者と比べて困り感が薄い」と判断されたのか、優先度が下がってしまった印象もありました。
我が家の選択とその後
結局、放課後等デイサービスは体験のみで本利用には至りませんでした。
その後は民間学童で宿題や音読を見てもらいながら、家庭でのフォローも続けています。家庭学習アプリや、ベネッセのまるぐランド、オンライン教材「すらら」なども併用して、子どもたちに合った方法を探ってきました。
情報収集の大切さを痛感した一方で、「家庭だけで抱え込むのは難しい」とも強く感じた体験でした。
まとめ|放課後等デイは学習障害の子に合うのか?
- 放課後等デイサービスは、学習支援も行っている施設もあるが、対象や支援内容にばらつきがある
- 支援級に通っていない子や軽度の困り感では、利用の優先順位が下がることもある
- 空きが出ないと利用できず、通所に時間や労力がかかるケースも多い
学習障害の子にとって、放課後等デイサービスは「合う・合わない」が施設によって大きく異なります。学習支援目的なら、早めに動いて見学・相談を重ね、自分の子にフィットする場所を見つけるのが成功のカギです。
そして、デイサービスだけでなく、家庭や塾、デジタル教材などさまざまなリソースを組み合わせて支援するのが現実的だと感じました。
お子さんの発達に不安を感じたら、まずは地域の教育センターや療育機関、自治体の相談窓口に問い合わせてみてくださいね。
▶︎ まるぐランド for HOME ─ ベネッセが“学習につまずきのある子”のために作った読み書き特化型学習
▶︎ すらら ─ 学年を問わず学べる元祖「無学年式」/教科書準拠で安心スタート勉強嫌い・苦手なお子さまの教材選びのポイント
- 無学年式(さかのぼり)学習に対応
- やさしく、つまずきにくい設計
- 読み書きの基礎力に特化
- 家庭学習が習慣化しやすい
▼資料請求は各公式サイトへ!
\今なら1ヶ月無料でお試し! /
【すらら】
\ 資料請求はこちらから /