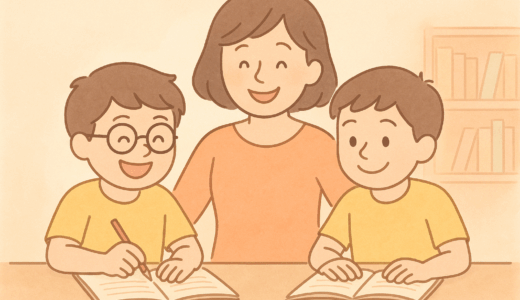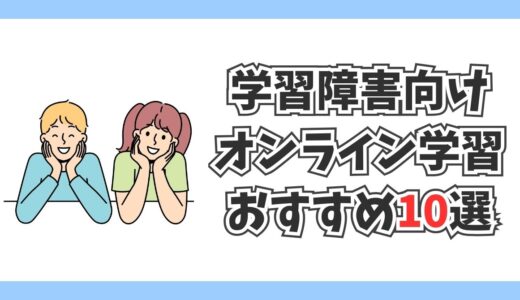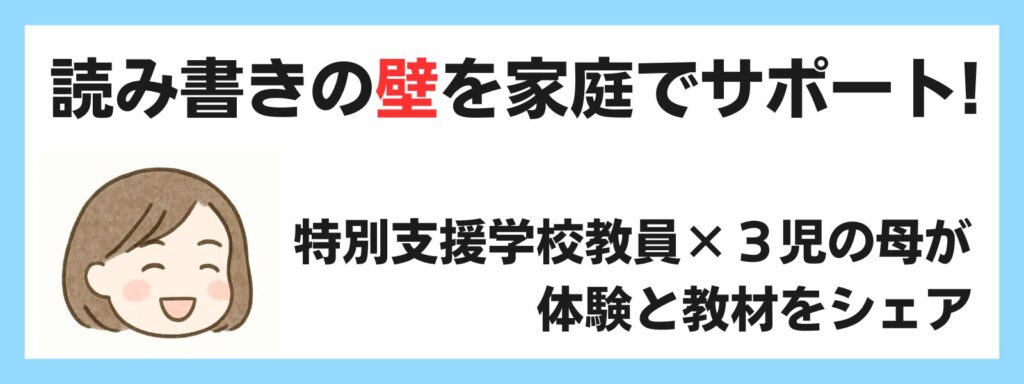
カテゴリ別に見る
人気記事一覧
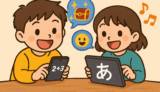
学習障害の壁を家庭で超える!計算・漢字が苦手な子向けおすすめ無料学習アプリ【小学校低~中学年向け】
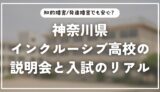
知的障害/発達障害でも安心?神奈川県立インクルーシブ高校の説明会と入試のリアル
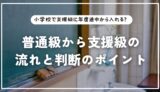
小学校で支援級に年度途中から入れる?普通級から支援級の流れと判断のポイント
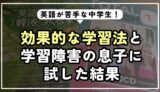
英語が苦手な中学生!効果的な学習法と学習障害の息子に試した結果

特別支援学校高等部で働いて感じたこと〜軽度知的障害のある生徒の学校生活と就労支援〜

[まとめ]LD・学習障害をサポートしてくれる機関、リンクをご紹介!
プロフィール


ぴーたん
25年間高校教員を勤め、現在は特別支援学校勤務。 これまで、多くの発達特性のあるお子さんたちと接してきました。 私自身、学習障害のある息子たちを育てながら、家庭と学校の両面からサポート。 このブログでは、保護者の「どうしたらいいの?」に寄り添い、実体験や役立つ情報をシェアしています。 さらに詳しいプロフィールはこちら。