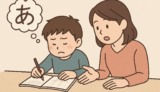「学習障害の子どもって、この先どうなるの?」
息子が年長のころ、私は毎晩のようにこの言葉を検索していました。
文字が読めない、数がわからない――。
診断もつかないまま、周囲と比べてできないことばかりが目につき、不安でいっぱいでした。
でも今、当時の子どもたちはそれぞれのペースで自分の道を見つけて社会に出ています。
長男、次男の2人は専門高校(工業高校)を卒業して、工場勤務で働いています。
息子たちのできないことに向き合い、早めの支援や環境づくりに取り組むことができました。
また、地元の「知的障害の子を持つ親の会」で似た特性のお子さんの成長を聞いたことも、“未来へのヒント”になりました。
学校生活・進学・就職・暮らしのこと――。
将来の姿を知ることで、不安が少し軽くなったのを覚えています。
この記事では、
- 就学前のわが子の発達の特徴
- 知的障害の子を持つ親の会で伺った、似たケースの子の将来
- 成人した息子たちの現在
- 学習障害や軽度知的障害のある子どもにとっての進路や将来の可能性
を、実体験をもとにわかりやすくお伝えします。
同じように悩んでいる保護者の方に、少しでも安心とヒントをお届けできたらうれしいです。

学習障害の息子2人の母
ぴーたん
25年間高校教員を勤め、現在は特別支援学校勤務。
これまで、多くの発達特性のあるお子さんたちと接してきました。
私自身、学習障害のある息子たちを育てながら、家庭と学校の両面からサポート。
このブログでは、保護者の「どうしたらいいの?」に寄り添い、実体験や役立つ情報をシェアしています。
さらに詳しいプロフィールはこちら。
就学前のうちの子の発達プロフィール:できないこと/できること

年長の息子について、当時の発達の様子を整理しました。
検査では田中ビネー式知能検査でIQ83、一部の分野では発達年齢が3歳程度という結果も出ています。
でも、数字だけでは分からない「得意・不得意」がたくさんありました。
学習障害の長男が苦手なこと(つまずいていたこと)
長男が年長のときにつまづいていたことは以下のとおりです。
- 数の理解:数唱は20まで言えるが、「これ何個?」と聞かれると2個以上は数えられない
- 記憶:2年以上同じクラスだった友だちの名前がほとんど覚えられない(「虫博士」などあだ名で呼ぶ)
- 言語理解:自分の年齢・誕生日が言えない/「いし」を「いち」と発音(構音障害)
- 読み書き:やっと自分の名前を読める程度。ひらがなを書くのは難しい
- 絵や図形:○や△などの基本的な図形が正しく描けない、歪んでしまう
- 時間の概念:「金曜日は○○のアニメがある」などの把握ができない
- 運動:縄跳びや竹馬など、複数動作の組み合わせが苦手(何度も練習してやっとできる)
- 社会場面での反応:緊張が強く、お遊戯会などで大きな声を出してしまうこともある
いや~、できないことだらけ。心配しかなかったですね。
学習障害の長男ができていること(強みや得意な面)
もちろん、できていることもあります。まあ、年齢相応と言えばそうなんですが…。
- 生活習慣:服の着脱、排泄、箸の使用、バンダナを結ぶなど、日常生活には支障なし
- 記憶の一部:カルタ・ことわざなどはしっかり覚えられる/訪れた場所の記憶も良好
- コミュニケーション:理由を説明できる・相手の気持ちを想像できる・遊びのルールも理解できる
- 人間関係:仲のよいお友だちが数人おり、関係性を築けている
- 言葉の理解:ゆっくりではあるが、やりとりには問題がなく、会話のキャッチボールができる
このように、「できないこと」にばかり目が行きがちですが、子どもなりに確実にできていることもありました。
それを見つけることで、支援の方向性が見えてきた気がします。
わが子と“そっくり”な子の今:知的障害の親の会で聞いたリアルな成長ストーリー
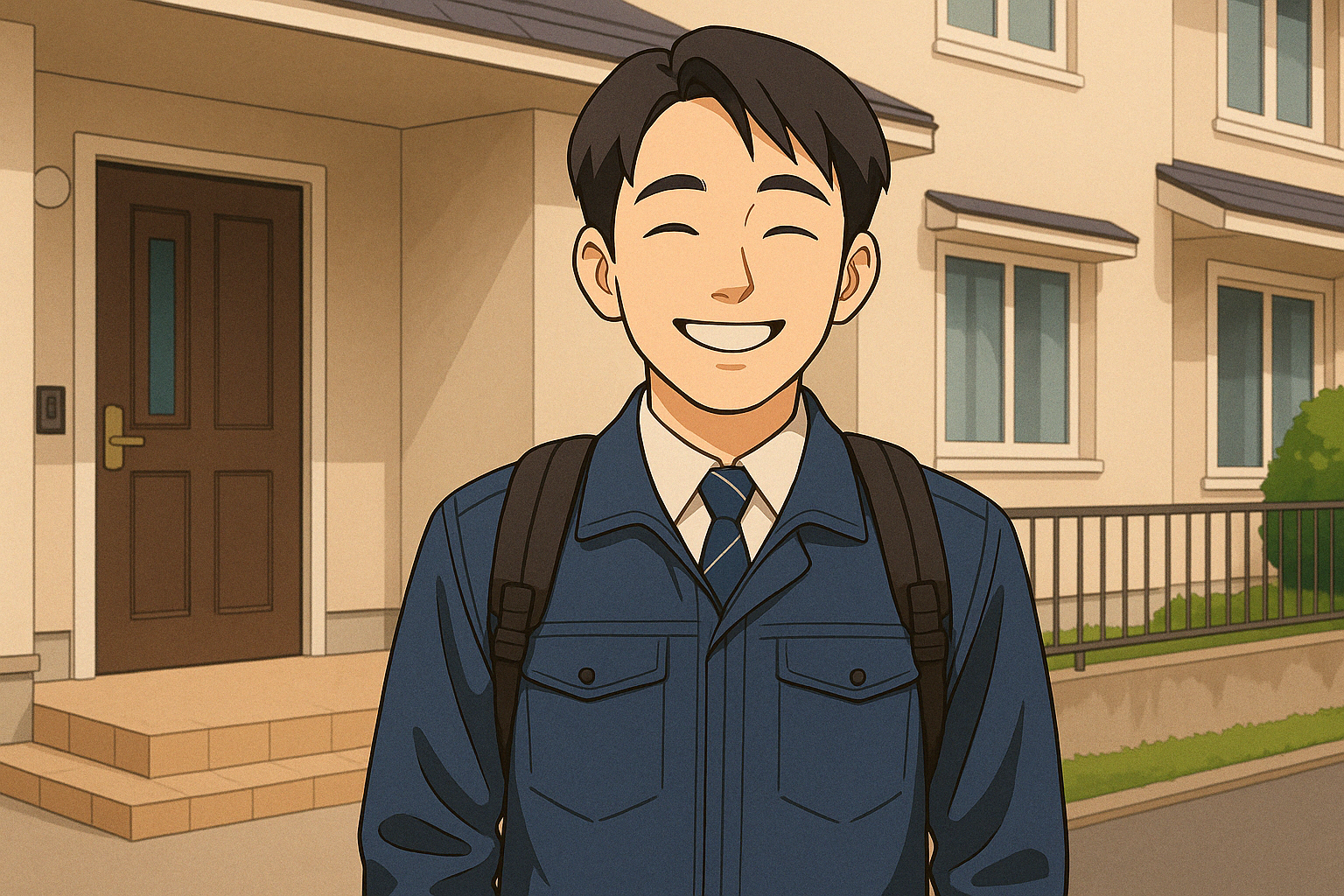
息子が年長の頃、私はずっと悩んでいました。
「この子は知的障害なのか、それとも学習障害なのか?」
「もし知的障害だとしたら、将来はどんな生活が待っているんだろう?」
田中ビネー式知能検査の結果はIQ83。
「年齢が上がるにつれて、IQは相対的に下がることもある」
と聞いて、ますます不安が募りました。
就学前の段階では、子どもがどこまで伸びるのか誰にもわからない。
誰か似たようなケースを知っている人がいないだろうか――。
そう思い、人づてに紹介してもらって、地元の知的障害の親の会の方に紹介をしていただき、地元で知的障害の方のグループホームなどを運営されている社会福祉法人の方お話を伺うことにしました。
似たケースのお子さんの成長ステップ
その方が紹介してくれたのは、わが子に“そっくり”な特性をもった男の子。
以下のような成長をたどったと教えてくれました。
- 幼児期から読み書き・数の理解に困難があり、「学習障害(LD)」と診断
- 発達障害のある子を受け入れている高校に進学
- 高校受験時の数学の能力も数直線を使って足し算・引き算というレベルだったが、サポートを受けて無事に卒業
- 卒業後、自動車免許を取得
- ヘルパー2級の資格を取り、介護職として就職
- 現在は、グループホームで生活しながら働く社会人
- 療育手帳(B2)を取得し、障害者年金と就労収入で自立した暮らしを送っている
軽度知的障害だと、療育手帳を取得できるのですね。読み書きや数の理解についてはうちの息子と同じような印象を受けました。
支援者の方の言葉に救われた瞬間
「人の気持ちがわかる子で、おしゃべりも上手。でもね、私の名前だけはなかなか覚えられなくてね~」
この言葉を聞いたとき、思わず
「それ、うちの子と同じです」
と返してしまいました。
人との関わりには何も問題がない。でも、学習や記憶が極端に苦手――。
そんな子にも、その子なりのペースと支援で、働いて暮らしていける未来がある。
そのことを、このとき初めて「実感」として持てた気がします。
成人したわが家の息子たちの“今”と、たどった道のり
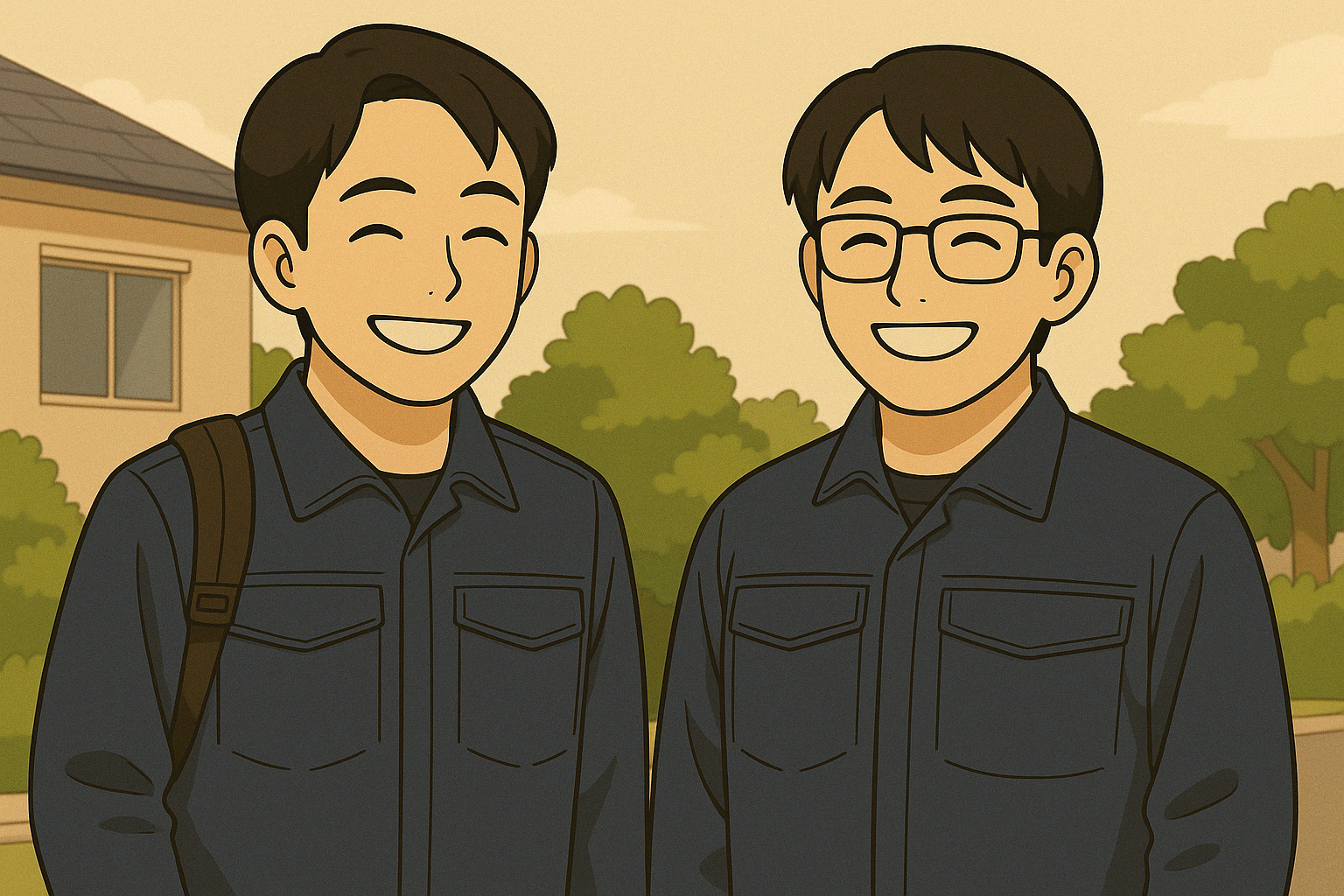
わが家には3人の子どもがいて、長男・次男はすでに社会人になりました。
2人とも中学時代は勉強が苦手で、成績はオール2〜2.5。英語のテストは、ほぼ“4択の運”まかせ……というくらい、苦戦していた教科もありました。
でもそんな2人が選んだのは、普通科ではなく工業高校の電気科。
「中学の苦手な教科を繰り返すより、新しいことを学んだほうが良いのでは?」と考えての進路でした。
高校での成長と得意を活かす環境
子どもたちは、高校でどんどん力を伸ばしていきました。
- 工業高校では、電気工事士2種や高所作業車の資格を取得(長男・次男)
- 専門科目の成績が良好で、ものづくりコンテストでも入賞(長男・次男)
- 長男は「数字の概念が入ってなかった」と言われた子だったのに、高校3年で数Ⅲを選択するほど数学に前向きに
- 長男は文字が読めなかったはずなのに、今ではラノベ(ライトノベル)を楽しく読んでいる姿も
次男は相変わらずマンガや本はあまり読まないタイプですが、TRPGの分厚いルールブックだけは興味津々。
夜な夜なオンラインゲームで友だちと遊び、キーボードも自在に打っています。学校の勉強が全てじゃないんだなと実感します。
社会人としての今と生活スキル
子どもたちが成人し、社会人になってからの生活をお知らせしますね。
- 高校の手厚い進路指導のもと、地元企業に就職
- 長男は社会人3年目、次男は新社会人としてスタートを切ったばかり
- 自宅から通勤し、毎月2万円を生活費として家に入れてくれています
- 長男はお金をあまり使わないタイプで、新NISAで積立もスタート
長男は残業が月20時間を超えることもあり、少し疲れ気味ですが、職場の先輩たちに可愛がられながら頑張っています
子どもによって「花が咲くタイミング」は本当に違う
小さい頃は、「この先どうなってしまうんだろう」と不安で仕方なかったけれど、子どもが興味を持ったことや得意なことを見つけられたとき、本当にぐっと成長する瞬間があるんだと感じています。
だから、今つまずいている子どもを見て「どうしよう」と感じている親御さんへ。
焦らなくても大丈夫。時間と環境があれば、ちゃんとお子さんの種は「その子なりに」ぐんぐん育つはずです!
知的障害?学習障害?就学前は“もやもや期”
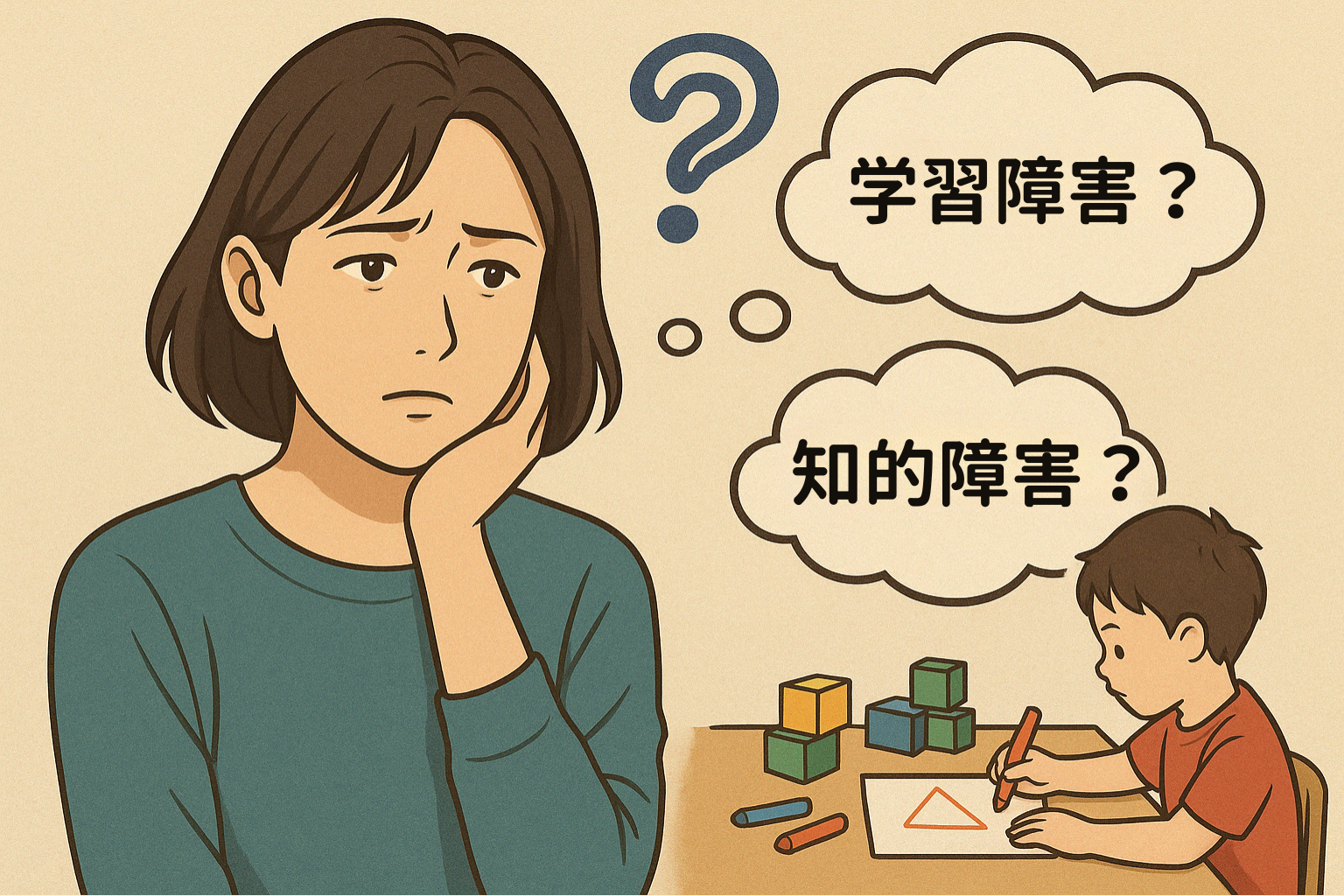
年長の頃、息子に明らかな発達の偏りが見えてきたとき、私はずっと
「この子は知的障害なのか?それとも学習障害なのか?」
と悩んでいました。
診断名がつかない時期こそ、親にとってはいちばん“もやもや”する時期だったように思います。
「知的障害だったら、どんな進路になる?」
「学習障害なら支援は受けられるの?」
と、いろいろな記事や本を読み漁りました。
知的障害と学習障害の違いって?
自分なりに調べて分かってきたのは、ざっくり以下のような違いです。
| 障害名 | IQの目安 | 特性の違い |
|---|---|---|
| 知的障害 | おおむねIQ70未満 | 全体的に発達がゆっくり。生活面や社会性も含めてサポートが必要なことが多い |
| 学習障害(LD) | IQはボーダー~平均以上 | 全般的な知的発達は問題ないが、読み・書き・計算など特定の分野で著しく困難がある |
ただし、実際はきれいに区別できるわけではなく、グレーゾーンにいる子どももたくさんいます。
療育機関でも「就学前では診断がつかないこともある」と言われ、ますます判断が難しい状況でした。
診断名よりも「子どもに合った支援」を
当時の私は「診断名がつかないと何も始まらない」と思い込んでいましたが、今振り返ると大事だったのは、“どんな特性があって、どこでつまずいているのか”を把握することだったなと思います。
診断名がなくても、子どもが過ごしやすくなる工夫や支援は始められます。
親が不安を抱えながらも、「今この子にできること」を一緒に見つけていくことが、いちばんの準備だったのかもしれません。
学習障害や軽度知的障害があっても、自分らしく歩める進路はある

「もしこの子が知的障害だったら、進学はできる?」
「就職なんてできるの?」
子どもが就学前の私は、こんな疑問をずっと抱えていました。
でも、学習障害や軽度知的障害がある子どもたちにも、いろいろな進路や働き方の選択肢があると分かってきました。
知的障害と診断された場合の主な進路・選択肢
療育手帳を持つことで、社会からのサポートを受けつつ生活できます。
- 療育手帳の取得により、さまざまな支援制度の対象に
- 高校進学:特別支援学校高等部、または支援枠のある全日制・定時制高校
- 卒業後の進路:
・就労継続支援A型/B型(福祉的就労)
・障害者雇用枠での就職
・グループホームでの生活 - 所得や状況に応じて障害年金の受給も可能
今は景気の影響もあり、軽度の知的障害のある方への就職の門戸はかなり広がっています。
「昔より働ける場が多くなっている」と感じています。
知的障害の診断がない(学習障害・境界域IQ)の場合
手帳がない分、自分で進路を切り開いていく必要性があります。
- 高校進学:本人の特性に合った高校選び(例:工業・商業・農業などの専門高校)
- 就職:高卒で一般就職 or 専門学校・短大・大学に進学
- 生活面:通勤・金銭管理など、自立に向けた支援は受けにくいが、工夫と支援で十分に可能
- 社会参加:本人の興味や得意なことを活かせば、「働ける」「つながれる」場所は必ずある
うちの長男・次男はまさにこのタイプでした。
中学では成績が振るわなかったけれど、工業高校で得意を見つけ、資格取得を通じて社会へ。今は立派に働いて、自分なりの将来を築き始めています。
大切なのは「制度」より「この子に合った環境探し」
診断名や制度ももちろん大切ですが、何よりも親として意識しておきたいのは、
「この子が安心して力を出せる環境はどこか?」
という視点です。
進学や就職の情報を集めておくことは、「選べる未来」を増やすことにつながります。
そして、本人の興味や得意なことを少しずつ見つけていくことで、自然と次の一歩が見えてくるものだと実感しています。
まとめ
学習障害を持っているお子さんの将来について、長男が年長のときに調べたことと、成人してからの様子をお伝えしました。
- 就学前の子どもの発達には、得意と苦手が混在していた(例:読み書きは苦手でも生活面は自立)
- IQ83、診断がつかないグレーゾーンのなかで進路を模索
- 親の会で「似た特性を持つ子どもが社会で活躍している」話を聞き、将来のヒントに
- 長男・次男は工業高校から就職、得意を活かして資格取得・社会人に
- 「子どもに合った環境探し」が、いちばんの支援
「学習障害かも」「知的障害だったらどうしよう」
息子の就学前、私は毎晩のようにネットで調べ、不安と混乱の中にいました。
それでも今、社会に出た子どもたちの姿を見るたびに、“あのとき悩んでいたことは、ちゃんと未来につながっていたんだ”と感じます。
文字が読めなかった子が本を楽しむようになり、計算が苦手だった子が資格試験に合格し、就職して毎日をしっかり生きている姿を見て、「子どもの可能性って、本当にわからないな」と思います。
支援や制度、進路の選び方――親ができることはたくさんあります。
でも一番大切なのは、「この子に合った環境を探そう」と諦めずに向き合い続けることかもしれません。
私の経験が、ほんの少しでもそのヒントになれたらうれしいです。
▶︎ まるぐランド for HOME ─ ベネッセが“学習につまずきのある子”のために作った読み書き特化型学習
▶︎ すらら ─ 学年を問わず学べる元祖「無学年式」/教科書準拠で安心スタート勉強嫌い・苦手なお子さまの教材選びのポイント
- 無学年式(さかのぼり)学習に対応
- やさしく、つまずきにくい設計
- 読み書きの基礎力に特化
- 家庭学習が習慣化しやすい
▼資料請求は各公式サイトへ!
\今なら1ヶ月無料でお試し! /
【すらら】
\ 資料請求はこちらから /