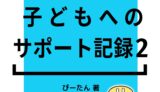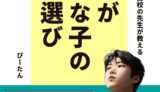「勉強が苦手になってきている小学生の子どもの進路が今から心配」
「子どもには大学に進んで欲しいと思っているけれど・・・実際には、高校でどんな進路指導が行われてるんだろう?」
子どもの将来への心配って悩みが尽きないですよね。
そんな保護者の方に向けて、Kindle本を執筆しています。とはいえ仕事をしながらの執筆がなかなか進まないため、書き上げたらどんどんブログにアップする形にしてみました。
執筆の手が止まらないよう、応援していただけると嬉しいです。まずは本の前書きです!ではよろしくお願いします。

学習障害の息子2人の母
ぴーたん
25年間高校教員を勤め、現在は特別支援学校勤務。
これまで、多くの発達特性のあるお子さんたちと接してきました。
私自身、学習障害のある息子たちを育てながら、家庭と学校の両面からサポート。
このブログでは、保護者の「どうしたらいいの?」に寄り添い、実体験や役立つ情報をシェアしています。
さらに詳しいプロフィールはこちら。
はじめに
はじめまして。ぴーたんと申します。この度は本を手に取って下さりありがとうございます。
この本を手に取ってくださった皆様、特に勉強が苦手なお子様を持つ保護者の方におかれましては、親として多くの悩みや不安を抱えることがあるのではないでしょうか。私自身も同じような悩みを持つ保護者の一人でした。
私は、高卒社会人と高校生男子の母であり、息子2人が学習障害(限局性学習症、読み書き障害など)を抱えています。息子たちに関しては、中学校時代に5段階でオール2を欠けるような成績を取ってきたこともあります。ほぼ皆勤で学校に通っていたにも関わらず、です。
「まさか、自分の子どもたちがこんなに勉強ができないなんて・・・」
定期テストの点数や成績表を見て、喜んだ記憶はほぼありません。
そんな私を助けてくれたのは、勉強が苦手な子どもたちが通う高校(以降、「進路多様校」と記載)の教員経験と、20年以上の進路指導のキャリアでした。
例えば、進路多様校に通う高校生にとって、大学受験のための「受験勉強」は小中学生のころから苦手とする学習方法です。専門学校を選ぶにも、首都圏には数多くの専門学校があります。高校生でも条件の良い会社に就職したいと考えています。
「受験勉強が苦手だけど、大学に入学できるの?」
「専門高校はどう選んだらいいの?」
「高卒でも正社員で就職できるの?」
など、そのような悩みを持つ生徒たちへの進路指導を、ほぼマンツーマンで行ってきました。
そして、進路多様校で生徒たちに進路指導をする中で、大学、専門学校、就職を含めた総合的な進路情報が少ないことに気がつきました。
ニュースでは、毎年1月に開かれる共通テストや大学進学率が話題に上がります。書店で進路に関する本を手にとってみても、多くは「大学受験案内」や「大学の過去問題」です。実際、高校生や高校生保護者に向けた進路全般について書かれた本はAmazonでもなかなか見つけられませんでした。
そんな中、お子さんの進路について悩むママ友から話を聞き、アドバイスをしていたところ、
「そんなこと考えたこともなかった」
「目からウロコだった」
と、気づきを得た!と感謝されることが度々ありました。
そこで私は、進路多様校の教員経験や進路指導のキャリアを活かし、保護者の方々に向けた進路に関する情報をまとめた本を執筆することにしました。
この本では、大学進学だけでなく、専門学校や就職についても詳しく解説しています。また、勉強が苦手なお子様に向けた進路の選び方についても紹介しています。
執筆にあたっては、私自身が経験したことや、進路多様校で生徒たちに進路指導をする中で得た知識やノウハウを基にしています。また、実際に専門学校の先生や企業の採用担当の方、学生の方々に話を聞き、その情報も盛り込んでいます。
この本で紹介するアドバイスやヒントは、あくまでも一例であり、全ての人に効果的とは限りません。しかし、お子さまに合った方法を見つけ、自信を持って進路選択に向けて前進するためのヒントやアイデアを提供することができれば、著者として大きな喜びを感じます。
最後に、この本がお子さまの将来についての考え方や学習の仕方に少しでも役立てば幸いです。保護者の皆様がお子さまのサポートをすることで、お子さまが自信を持って進路を選択し、夢を叶えることができるよう、心よりお祈り申し上げます。
高校生でやりたいことは見つかるのか?
高校生には、自分がやりたいことが見つからないという悩みがあるようです。
リクルート進学総研が2021年に行った調査によると、進路について気がかりなことを尋ねたところ、「学力が足りないかもしれない」という悩みが最も多く(55%)、次いで「やりたいことが見つからない」「自分に合っているものがわからない」という悩みが高かった(それぞれ36%、35%)。
実際、やりたいことが決まっている高校生はそんなに多くありません。だからこそ、高校生のうちにやりたいことが見つかるわけではなく、見つけるべきだというプレッシャーをかけすぎないようにしたいものです。
また、やりたい仕事が見つかったとしても、それが本当に自分に合っているかどうかはわかりません。実際にやってみてはじめて分かることもあるでしょう。
社会で働く人が全てやりたいことを仕事にしていたら、必要な仕事が人手不足になり社会が混乱してしまう可能性もあります。収入を得るためには、自分がやりたいことと割り切って、別の仕事に就くことも必要かもしれません。
保護者や進路指導者は、「小さい頃から夢を持とう」と言うことがありますが、それは必ずしも正しいわけではありません。子どもに「ただ一つの天職がある」という考え方を暗示してしまっていませんか。それは、学校の良くないところである「正解主義」であるとも言えます。(よくないね~!)
時代の流れも早くなっている今、将来の仕事もどうなっているか分からないため、柔軟な考え方が必要です。
親の世代はやりたいことがあったの?
「この子、何に興味があるのかわからなくて困っています」
と、保護者の方が三者面談で嘆くことがあります。
そんな時、私がよく聞くのが
「お母さんは進路を決める際に、自分のやりたいことを持っていましたか?」
という質問です。
すると、ほとんどの場合、こんな答えが返ってきます。
「私が就職活動をしていた頃は、バブル全盛期でした。その時代は、自分が何をしたいのか考えなくても、多くの内定を得ることができました。だから、特にやりたいことを決める必要はなかったのです。」
と。つまり、やりたいことがなくても、進路を決めることは可能だということです。(最近は、氷河期世代の保護者の方がほとんどなのでこの問いかけは当てはまりませんが…^^;私もです!)
ただ、失われた30年と言われた低成長時代は、若者が正社員になることが難しくなっていました。そのため、狭き採用の門を突破するためには自分自身を分析し、自分がなぜその会社を選ぶのか、自分が何をしたいのかを考え、理由をつける必要があります。
今でも、そのような状況が続いています。
進路を考える上で、今の高校生たちの状況は、親の世代とは全く異なります。やりたいことが決まっている場合は、進路を拓くために有利に働くかもしれません。しかし、やりたいことが見つからない場合もあります。
「高校生にはやりたいことがあることが当たり前で、大学に入れば道が開けるだろう」という価値観をお子さんに押し付けるのはやめた方が良いと思います。
大学・専門学校への進学を選ぶ生徒の意識
大学生の進学理由としては、「大学で過ごすこと自体が人生経験として重要だと思ったから」が 74.4%と最も高く、次いで、「先行き不安な時代に大学くらい出ていないといけないと思ったから」が 73.1%となっています。
>>大学におけるキャリア形成支援とキャリア教育 (厚生労働省・2014年)
大学生に、大学への進学理由を聞いたところ、「すぐに社会に出るのが不安だから」「自由な時間を得たいから」「周囲の人がみな行くから」と消極的に考えている者が、職業を意識した時期が遅いほど顕著という傾向があります。
>>進路を考える時の高校生の気持ち(文部科学省・2007年)
志望校選びの際「重視するポイント」は、前年同様「学べる内容」が上位にランクインしました。進学先区分別にみると、大学・専門学校への進学者は「学べる内容」が、短期大学への進学者は「取れる資格」がトップ項目となっています。
専門学校進学者の約4人に3人が、一定の職業イメージ・学習イメージを有して専門学校進学を決定しています。大学進学者においてはここまで高い職業イメージを持ってはいないと思われます。専門学校進路決定において、その多くが具体的な職業イメージやそれに関連する学習イメージを持っていることが確認できます。
「美容・理容系」や「エステ・ネイル・メイク系」「音楽・アニメ・芸術系」「ペット系」などは大学と競合する学科がないため専門学校のみを検討した生徒が多く、また進学を検討した時期も他の学科と比較すると早い傾向があります。
専門学校に進学した生徒の理由として「高卒で就職したくなかったから」を上げている生徒は、「ビジネス・経営・事務・秘書系」に進学する傾向が高いです。これら実務系への専門学校進学が高卒就職の代替として機能していると考えられます。
>>進路決定過程と進学要求からみる専門学校進学者の特徴(ベネッセ教育総合研究所・2017年)
>>高校生の進路意識と進路選択に関するアンケート調査 – マイナビ進学総合研究所(2021年)
公務員や警察官になるために通うような、「資格の◯◯」といった就職予備校的な専門学校をイメージしてもらえば良いと思います。
就職を選ぶ高校生の意識
2021年に全国で開かれた合同企業説明会に参加した約1.000名の高校生にアンケートを取った際の結果です。
高校卒業後に就職しようと思っている理由を質問したところ、「早く自立したいため」が一番多く42.4%でした。次いで「家庭の経済的理由」が22.4%、「就きたい職業が決まっているため」が17.9%でした。
就きたい職業が決まっている、目標があるなどの回答も含め、「早く自立したい」というポジティブな意識が高校生に多く見られる結果となりました。
>>高校生の就職活動に関するアンケート調査2021年(7月)コロナ禍就職希望の高校生6割「就職できるか不安」、就職する理由の1位は「早く自立したい」が4割(ジンジブ・2021年)
私が以前担任していたときに、施設から通ってる生徒がいました。「高校卒業までは施設に住むことができるが、卒業したら住み込みで仕事ができる起業に就職しなければならない」という話を聞いて切なくなったことがあります。
進路に「正解」はない
進路に「正解」はあると思いますか?
三者面談で保護者の方と話していて気になるのは、進路に「唯一の正解がある」と思っていらっしゃることです。
- とにかく大学に行ってほしい
- 偏差値の高い大学でなければならない
- 大学に行かなければ一生安い賃金で働くことになる
このような考えにとらわれている保護者の方がとても多いです。
しかし、昭和ならいざ知らず、現代の令和の時代では主要産業がどんどん移り変わります。経済の流れが以前の数倍以上早い現代において、「唯一の正解」を求めてしまうのは危ういなと感じます。
私の考えは、
「いま現在で、よりマシな進路を選ぶ」
ということです。
誰しもが、将来の見通しが難しい時代に生きており、一度きりの進路選択で全てが決まるわけではありません。
将来、興味や必要性を感じた時に再度学びの場に戻ることもできます。人生は長いものであり、平均寿命が約85歳と言われています。18歳から引き算すると65年以上あります。
18歳での進路選択がその後の人生に100%影響すると考えてしまうと、逆に怖くなり一歩も踏み出せなくなってしまいます。
進路は、時代や景気の影響を大きく受ける
また、高校卒業後の進路は時代や景気に流されるのが一般的です。
バブル時代に学生だった人は、新幹線の交通費まで出してもらえて内定が何十社ももらえたり、逆に就職氷河期に学生だった人は、正社員になれないまま40代になってしまったりと、時代の影響を大きく受けます。
そして皆さんも感じている通り、現在は将来を見通すのが非常に難しい時代になっています。
2020年に行われるはずだった東京オリンピックの2年前(2018年)の進路指導の際には、
「大学に入学した場合、オリンピック開催後に就活することになる。景気後退をしている可能性があるから就職活動の難易度が上がるのではないか」
との情報があり、面談時には将来の景気についての予測を伝えていました。
しかし、2020年から始まった新型コロナウイルス感染症のまん延により東京オリンピックは1年延期。また景気も予想よりも大きく後退し、業種によっては多くの企業が倒産するような事態に陥ってしまいました。
未来の大まかな方向性は見据えつつも、サーフィンをするように時代の波を読み、そして波に乗っていくための努力がより必要とされています。
生徒の能力に幅がある、進路多様校の実際
進路多様校での実際の状況や、生徒の能力の多様性についてお伝えしたいと思います。
偏差値が40前後の高校は「進路多様校」と称され、時には「教育困難校」とレッテルを貼られることもあります。私が進路多様校で働く中で気づいたことは、生徒たちの能力にはかなりの多様性と幅があるということです。
進路多様校には、中学校の内申点がオール2からオール2.5前後の生徒が入学してきます。内申点の分布を見ると、平均的にオール2だったり、特定の教科に1がついていたり、3があったりと、生徒たちの能力には大きなばらつきがあります。中には小中学校で通級指導教室に通い、学習障害が指摘されている生徒や、グレーゾーン・境界知能の生徒も存在します。
例えば、英語の場合、アルファベットの小文字の「b」と「d」が覚えられない、アルファベットが古代文字に見えるという生徒もいれば、高校で英語学習のモチベーションが湧き、コツコツと勉強し、英検2級を取得する生徒もいます。さらに、学校が提供する短期留学プログラムに参加し、帰国後は流暢な英語で留学の報告をする生徒もいるほどです。
また、国語、英語、社会など特定の科目に限定すれば、大学進学のための学力を持つ生徒も少なくありません。
しかし、日本の学校では、できない科目を減らすよう指導されることがよくあります。このような状況下で進路多様校の生徒に、「全科目の勉強ができない子」「勉強が苦手な子」というレッテルを貼ってしまうことは、あまりに大雑把な見方ではないでしょうか。
さらに、生徒たちが口にするつぶやきも気になります。「どうせ◯◯高校だし」とか、「自分はダメなやつなんだ、人生終わった」といった言葉が出てきます。彼らは自己評価を0か100で判断しており、自己評価が低くなっていることがつぶやきに表れています。
「まだまだ人生は長いのだから、そんな風に思わなくても大丈夫!」と声をかけてはみますが、彼らは小中学校から長期間にわたって低評価を受け続けてきた生徒たちです。教員の声かけだけでそんな考え方が変わるようなら苦労はしません。
彼らが自信を持てるようにするためには、どのようなアプローチが効果的なのか、教員たちも悩んでいます。
進路多様校は、進路を自分で選ばなければならない
進路多様校では、生徒たちが自分で進路を選ばなければなりません。当然ながら、生徒の学力や能力が多様であるということは、選ぶ進路も多様であるということです。
かつて、子どもが多かった時代には専門学校や就職を選ぶ生徒の割合が高かったです。しかし、現在では少子化という要因もあり、多くの進路多様校では、大学・短大進学者が30〜40%前後、専門学校進学者が40%前後、就職が5〜10%前後となっています。また、未決定者も一定数存在します。偏差値が40台だからといって、大学進学ができないというわけではありません。
進学校に通っていた方にはイメージが湧くかもしれませんが、大学進学率が100%の高校では、大学化、専門学校、または就職かと進路先に悩む必要がありません。「同級生が大学に行くから」「大学以外の進路を考えたことがない」という理由で、自分の学力や興味に合った大学を選び、推薦入試や一般入試に臨めば良かったのです。
一方、進路多様校では、卒業時点で大学、専門学校、就職といった広い範囲から自分で進路を選ばなければなりません。服装や髪型、選択授業など、何かと「お友達と一緒」が好きだった彼らであっても、進路に関しては「お友達の◯◯ちゃんと同じ学校に行きたい」という生徒はいません。
最終的には教師や保護者と面談しながら、自分で行動を起こす必要があります。例えば、オープンキャンパスに参加するなど、自ら動いて自分なりの進路を形にするのです。
これが、偏差値50以上の高校と進路多様校の違いの一つと言えるでしょう。
頑張っている卒業生も多い
進路多様校では、進路を切り拓くのは難しいのではないかと思われる方も多いかもしれません。実際には、発達障害や貧困といった困難な状況にある高校生を取り上げた書籍もいくつか出版されています。しかし、そこに通う生徒がすべて困難を抱えているわけではありません。
実際のところ、進学した卒業生の中には大学に進学し、3年後に教育実習に来て立派に研究授業をやり終える人もいます。先日、就職内定を報告しに来てくれました。
美容師の専門学校に進学、その後店長になり、複数の店舗を任されて報酬を得ている卒業生もいます。さらに、鉄道会社で運転手として働いている卒業生や、ユーチューバーとして数百万人単位のチャンネル登録者を持ち、テレビにも出演している卒業生もいます。数え上げればきりがありません。
進路多様校に進学したからといって、その後の人生が終わったと考える必要はありません。ただし、卒業後に進路が未定のままフリーターとして働いている卒業生や、大学を中退して進路が決まらずにアルバイト生活を送っている卒業生も存在します。
こうした事例を通じて、進学先や進路がどうであれ、生徒たち一人ひとりには可能性があり、将来を切り開くチャンスがあることをご理解いただきたいと思います。
続きはKindleで!
おかげさまで、「勉強が苦手な子の進路選び」はKindleで出版しています^^。
ぜひ、読んでみてくださいね♫