こんにちは。ぴーたんです。
この春から特別支援学校の高等部で働き始め、半年が経ちました。軽度知的障害の生徒を対象にした特別支援教育の体験を記しておきたいと思います。
「支援学校にはどんな生徒が通えるの?」「どんな授業が行われているの?」といった疑問をお持ちの方も多いと思います。
私も発達障害の息子の進路先について調べるのに大変苦労しました。そこで今回は、簡単に勤務先の様子をお伝えしていきます。
以下のような方におすすめします。
- 発達障害または軽度知的障害のお子さんの保護者の方
- 支援学校への進学を考えている方
- お子さんの進路について不安のある方
あくまで、私の勤務先の様子なので、一例として読んでみてください。一般的な特別支援学校の状況ではありませんので、ご自身の目で地域の特別支援学校を確かめてくださいね。
自治体によっては、軽度知的障害のある生徒の将来の就労を見据えた高等支援学校が設置されています。私が勤務している学校も、そのような制度に近い支援学校の一つです。
目次 閉じる
特別支援学校高等部で働いた感想
まず、この春から働き始めた感想をお話しします。控えめに言っても、とても楽しく充実した生活を送っています。
前職ではフルタイム勤務でしたが、今の仕事は短時間勤務の非常勤なので、働き方自体にゆとりがあります。担任は持たず、基本的には生徒が来てから帰るまで授業や実習の指導をする毎日です。
生徒の課題は個別かつ具体的です。指示された作業や仕事について、できないことをできるようにしていく支援や、就労を目指して社会人としての資質や態度を身につけるためのサポートをしています。
できない生徒がいても、「伸びしろ」にしか見えません。「今できなくても大丈夫」と励ましながら指導しています。
以前勤めていた高校では、1クラス40人の中にいる少数派の発達障害や知的障害の生徒へのいじめや人間関係のトラブルが起きやすく、指導に困難を感じることが多くありました。
一方で、支援学校では、1クラスが少人数で構成されていてそれぞれがユニーク。個性強めな子どもたちが集まっているという印象です。「障害」というよりは「個性」と思って接しています。
知的障害と発達障害の生徒の違い
知的障害と発達障害はどう違うの?という方へ、まとめてみました。
| 知的障害 | 発達障害 | |
|---|---|---|
| 定義の 違い | 一般的な知的機能が平均よりも顕著に低く、日常生活のスキルにおいても制限がある状態。 全般的な知的能力の低さが特徴 | 生まれつきあるいは幼少期に発症する、特定のスキルや機能の発達が遅れることを指す障害。 言語、運動、社会的スキルなど、特定の領域における遅れが中心 |
| 診断 時期 | おおむね18歳までに知的機能の障害が表れる。 軽度知的障害の場合、IQの低さは通常6歳以降に明確になることが多い | 知的障害よりも低年齢で診断されることが多い |
| 障害の 範囲 | 全体的な知能の遅れが見られる | 特定の領域(読み書き、計算、社会性など)に限定された困難さがある |
| 福祉 制度上 の違い | 「療育手帳」の交付対象となる | 「精神障害者保健福祉手帳」の交付対象となる |
以前の職場では、発達障害の生徒と多く接していました。知的障害の生徒はどんな特徴があるのだろうと思い勤務してみましたが、見た目で障害がわかる生徒はほとんどいません。
話してみると、「この子、ちょっと天然だな」とか「思い込みが強めだな」とか「多少コミュニケーションが苦手なのかな」と思う程度です。
とはいえ、知的障害のある方の約30〜40%が自閉症スペクトラム障害(ASD)の特性も持っているという研究結果があります。生徒の個人票を見ると、LDや注意欠如・多動性障害(ADHD)が併存されている方も多いです。
我が家には学習障害の息子たちがいて、漢字がとても苦手です。それに比べて、知的障害の生徒の中には漢字検定4級を取れる生徒もいて、とても驚きました。ただ、漢字は書けてもその漢字が意味するところを理解してコミュニケーションを取るのが苦手だったりはします。
一方で、英語はどの生徒も苦手です。導入のルーティンで「日付」「天気」を聞く課題があったのですが1年経っても日付と天気を聞く質問が理解できなかったとのこと。また、数学の抽象的な概念も苦手な傾向にあります。計算能力については、xやyなどの代数がわかる生徒もいる一方で、10+10はわかっても15+12は瞬間的にわからない生徒や、足し算引き算はわかっても割り算までは難しいという生徒もいます。
この辺りは、それぞれの発達の凸凹や苦手な分野が違うのだなと感じています。働き始めて読んだ本はこちらです。早期の手当てと、ゆっくり長い目で子どもの発達を見ていく重要性が分かる良本です.
特別支援学校高等部の入学について
勤務先の生徒は、自力で通学できることが条件で入学してきます。IQが50から75程度で、ほとんどの方がB2またはB1の療育手帳を持っています。療育手帳があることで、障害者枠での就労や、就労支援A型・B型の利用が可能になります。
療育手帳の種類と判定基準
ここで、知的障害の種類についてまとめておきますね。
| 一般的な呼称 | IQ目安 | 障害の状態 | |
|---|---|---|---|
| A1 | 最重度 | 20以下 | 生活全般にわたり常時個別的な援助が必要。 言葉でのやり取りや身近なことの理解も難しく、意思表示はごく簡単なものに限られる。 |
| A2 | 重度 | 21~35 | 社会生活には個別的な援助が必要。 単純な会話はできるが、読み書きや計算は不得手。 日常生活では個別的援助を必要とすることが多い。 |
| B1 | 中度 | 36~50 | 何らかの援助のもとに社会生活が可能。 ごく簡単な読み書き計算ができるが、生活場面での実用は困難。 日常生活では声かけなどの配慮が必要。 |
| B2 | 軽度 | 51~70/75 | 日常生活は一人でできるが、社会生活への適応に適切な援助が必要。 抽象的な思考推理が困難。 |
そのため、療育手帳をお持ちでない発達障害のお子さんには、残念ながら入学はおすすめできません。例えば、発達障害があってもIQがグレーゾーンの生徒が入学した場合、障害者雇用も就労支援も難しくなってしまいます。
また、支援学校の卒業後は進学を希望する生徒もいますが、高等支援学校は高校ではないため高卒の資格は取れません。高卒資格を得るためには、別途高卒認定試験を受ける必要があります。
授業内容も、高校生が履修する内容とは異なります。知的障害のある生徒のための教科書を使用し、実務的な内容がメインです。例えば、国語では遅刻時の電話のかけ方、数学では時間の読み方など、実践的な内容を学びます。学習レベルとしては、小学校高学年程度のイメージです。
履修内容やカリキュラム、入学の目的をよく理解しないまま入学し、ミスマッチを起こして退学する生徒さんもいるようです。進学希望の場合は、支援学校よりも通信制高校などの選択肢を検討した方が良いかもしれません。
私の知人には、お子さんが一般の高校生と一緒に学びたいという希望があり、知的障害の生徒を受け入れている普通高校で3年間を過ごしました。
不登校になるケースもありますが、学校としての対応には限界があります。保護者が良かれと思っても、本人の意思がない場合は、無理に入学させることはしないほうがいいでしょう。
入学する生徒の多くは、自身の障害を理解しており、小学校や中学校で支援級を経験しています。
また、小学校から支援級に在籍していても、それは必ずしも障害が重いということではありません。保護者の判断で早期から支援級を選択し、実際の知的能力はそれほど低くない生徒もいます。
特別支援学校高等部の生活の様子
生徒の学校生活は、メンバーの知的能力や社会的な能力によるところが大きいです。穏やかな生徒が多ければ落ち着いた学校生活になりますが、情緒的に不安定な生徒が入学すると、人間関係のトラブルが頻発することもあるようです。
支援学校と一般的な高校の大きな違いは、人間関係のトラブルへの教員の関わり方です。支援学校の方が、教員が積極的に介入する傾向にあります。
主なトラブルとしては、以下のようなものがあります。
- 入学時の生徒同士のトラブル
- 先輩・後輩関係のトラブル
- お金に関するトラブル
- 異性関係のトラブル
スマートフォンは多くの生徒が普通に使いこなしているため、LINEなどでのトラブルも見られます。
放課後の過ごし方も生徒によって様々です。友達と遊ぶ生徒、放課後等デイサービスに通う生徒、飲食店やコンビニエンスストアでアルバイトをする生徒など、それぞれの能力に応じた活動をしています。
また、男女の入学者の比率が同じくらいになると、恋愛関係のトラブルも増える傾向にあります。生徒同士の恋愛関係や、その進展を教員が把握していることも、一般の高校との大きな違いだと感じています。
特別支援学校高等部の進路指導について
年に数回、企業や就労支援施設での実習があります。教員は実習先の開拓や、生徒との面接練習、通勤練習のサポートなど、様々な準備を行います。
実習後は、お礼状の作成指導も行います。きれいな文章が書けるまで、何度も書き直すこともあります。
支援学校は教員の数が多く、恵まれた環境だと感じましたが、実習指導やインターンシップ先への訪問、開拓、通勤練習、巡回などで、ほとんど毎日出張している先生もいます。そのため、現場が手薄になることも少なくありません。
生徒が10人いれば、実習先も10通り。就職先も違えば、得意なことも違います。
生徒によっては一度で適切な実習先が見つからないこともあります。また、実習を受け入れてもらえても就労までは難しかったり、家族が就労を望んでいても生徒の能力的にはA型やB型の就労支援が適している場合もあり、その判断のための面談も教員の重要な仕事の一つです。
進路指導については、先生方はかなり精力的に取り組んでいます。就労支援施設の方々に来ていただいて話を聞く機会を設けたり、実習の報告会を開催して生徒のプレゼン能力を高めたりしています。
先生方は生徒のためにハローワークへ行き、障害者向けの一般就労を行っている会社にアポイントを取ったり、周辺の支援学校と協力して情報交換したりと、熱心に活動しています。
また、学内の職業のために、企業様からの仕事を受けられるよう営業してくることも。職業の時間では、ダイレクトメールの折りやタオルたたみ、100円ショップで販売される商品の袋とじ作業なども行っています。100円ショップで商品を見かけるたびに「これも誰かがラッピングしてるんだな~」と考えるようになりました。
このような環境も支援学校によって大きく異なり、都市部に行くほど企業が多く、就労の機会に恵まれているように思います。私が勤めている地域はそれほどの大都市ではないため、製造業からサービス業、清掃まで、様々な分野で仕事の機会を見つけられるよう、先生方が日々開拓に努めています。
まとめ
以上、高等支援学校の高等部に半年間勤めて感じたことをつらつらと書かせていただきました。
前の職場でもやりがいはありましたが、今は生徒だけに関われるという恵まれた環境の中で、生徒の将来や現在の生活がより良くなるように貢献したいという気持ちで働いています。
どのような接し方が望ましいかなど、ベテランの先生方からお話を聞いて日々学んでいる最中です。
普通高校と比べて1クラスの人数が少なく、先生方が手厚く指導できる環境です。また、授業もティーム・ティーチングで行うため、生徒が集中して学べる環境が整っていることもありがたく感じています。
非常勤のため、来年はまたどこで働くことになるか分かりません。とりあえず、この1年は楽しんで働くことができそうです。1日1日を大切にしながら日々過ごしていきたいと思います。
ここまで読んでくださり、ありがとうございました。


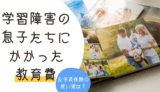
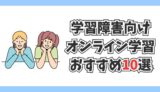
現在年少の男の子がおり、ウィスク67で知的支援学級を勧められましたが、支援学級は支援専門の先生ではないと知り、支援学校にした方が良いのでは?と悩んでいましたが、支援学校でのカリキュラムやその後の進学や就職の行方を知り、我が子には支援学級が適していると理解納得できました。
ありがとうございました。
お子さんの就学先、本当に悩まれたことと思います。
支援学級か支援学校か、どちらがお子さんにとってより良い環境なのか、情報を集めて考えるのは大変ですよね。
そのお気持ち、とてもよく分かります。
ご自身でカリキュラムや卒業後の進路までしっかりと調べ、最終的にお子さんには支援学級が合っていると納得できたとのこと。
保護者の方が納得して「ここだ」と思える場所が見つかることが、お子さんにとっても一番の安心に繋がりますものね。
まだ、年少ということなので様子を見ていっても大丈夫ですよ~。
こちらこそ、とても貴重な経験を教えていただき、ありがとうございました。